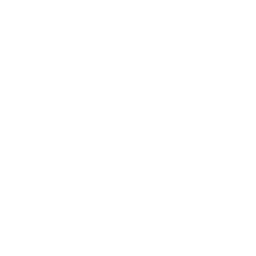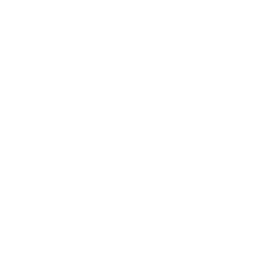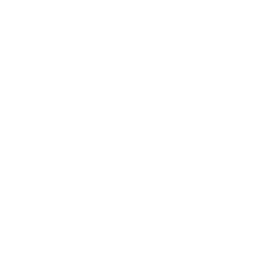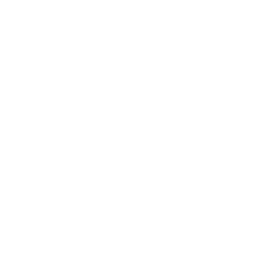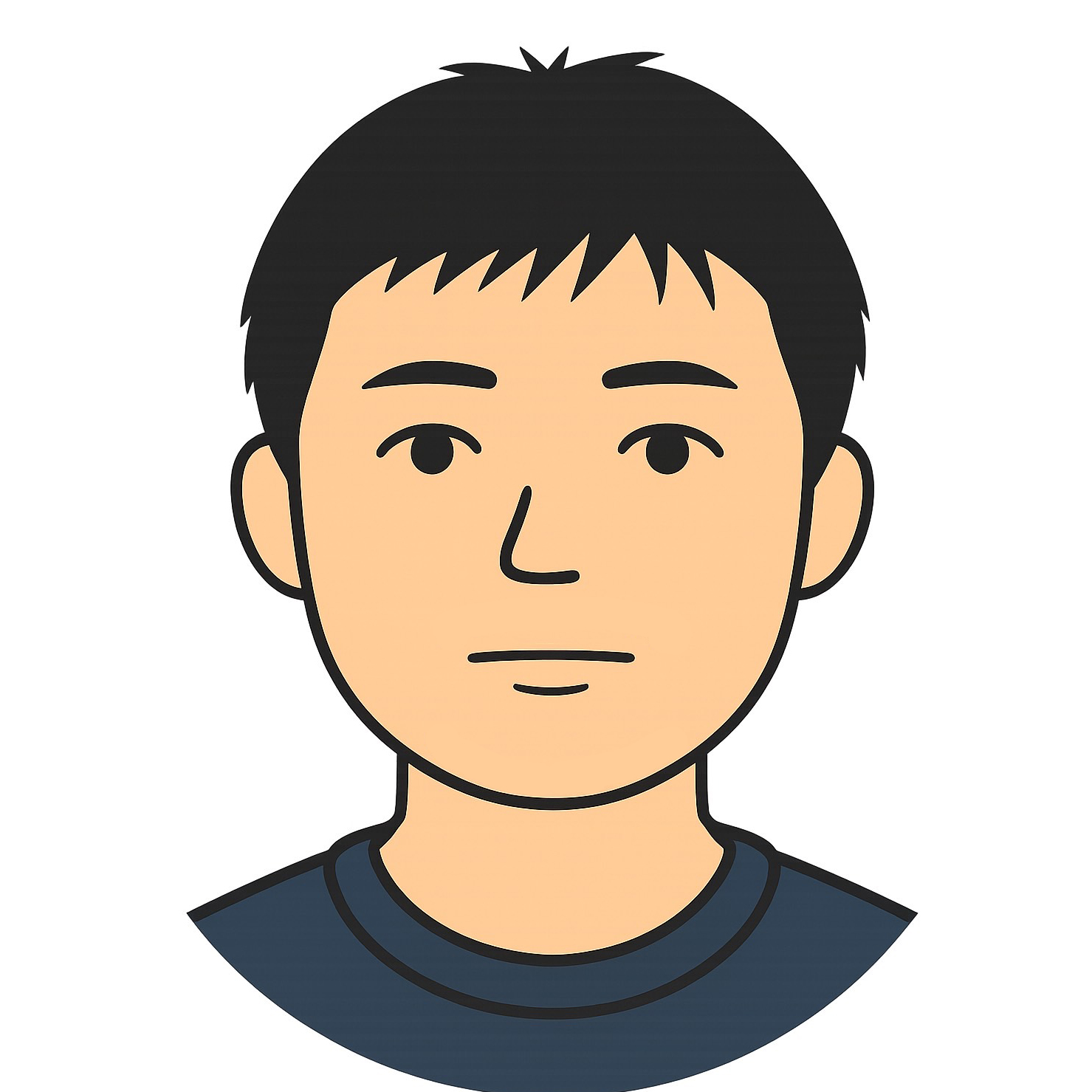
国産離れ?コスト高?それでも割り箸が選ばれる理由とは──今どきの割り箸事情
「SDGs」「エコ」「コスト削減」──そんな言葉が飛び交う中で、飲食業界の消耗品にも変化が起きています。
その代表例が「割り箸」。国産材の確保が難しくなり、輸入品の価格も上昇。竹箸・プラスチック箸・リユース箸との選択も複雑になる中で、割り箸は今どう位置づけられているのか。
実際に製造現場にいる私たちから見た、今どきの割り箸事情をお届けします。
✅ 1. 「国産割り箸」が減っている理由
かつては日本各地で作られていた国産の割り箸。しかし現在、日本で流通している割り箸の多くは中国などの海外製が占めています。
背景には、林業の衰退・後継者不足・国産材の価格高騰といった構造的な問題があります。特に手間のかかるひのきや杉の間伐材を割り箸に加工するには、高度な技術と人手が必要で、安定供給が難しくなっています。
弊社では現在も、奈良・吉野の職人さんに割り箸の製造をお願いしていますが、平均年齢はすでに80歳近くに達していると聞いています。
長年の経験に支えられた貴重な技術ではありますが、このままでは次世代につなげるのが難しいという深刻な課題も見えてきています。
✅ 2. 輸入割り箸も値上がり中?
「じゃあ安い中国製でいいや」と思うのは早計です。近年では海外製割り箸の価格も上昇傾向にあります。
要因は、現地の人件費上昇、物流コストの高騰、為替変動、さらには日本の輸入依存度の高さです。とくに2023年頃からは、1膳あたりの単価が1.5~2倍になった品種も珍しくありません。
✅ 3. 「再利用箸」に潜む意外なコスト
リユース箸(洗って繰り返し使う箸)を導入する飲食店もありますが、実は導入コストや洗浄・衛生管理の手間、顧客心理の不安など、見えにくいコストもあります。
その点、割り箸は「使い切り」の気軽さと、衛生面の安心感が支持されています。
✅ 4. 今、飲食店が求める「ちょっといい割り箸」
最近では、「安さよりも雰囲気やブランド価値を重視する」お店が増えています。
箸先の形状や木の質感、焼印や帯デザインにこだわることで、おもてなしの気持ちを表現する道具として割り箸を見直す動きも出てきています。
🔹 高級店では「ひのき材・杉材」の割り箸
🔹 居酒屋では「名入れ帯付き」や「丸箸」で差別化
🔹 エコ意識の高い店では「竹箸」や「間伐材」のPR
✅ 5. 割り箸は“消耗品”から“価値を伝えるツール”へ
割り箸は単なる消耗品ではなく、店の個性や姿勢を伝えるツールになりつつあります。
SDGsや衛生意識の高まりを背景に、「安心」「清潔」「日本らしさ」を形にできるアイテムとして、見直される存在です。
時代が変わっても、人が食事をする限り「箸」は必要です。
その中で、割り箸という選択肢は今も、そしてこれからも、“心地よい一膳”を届けてくれる存在であり続けるでしょう。